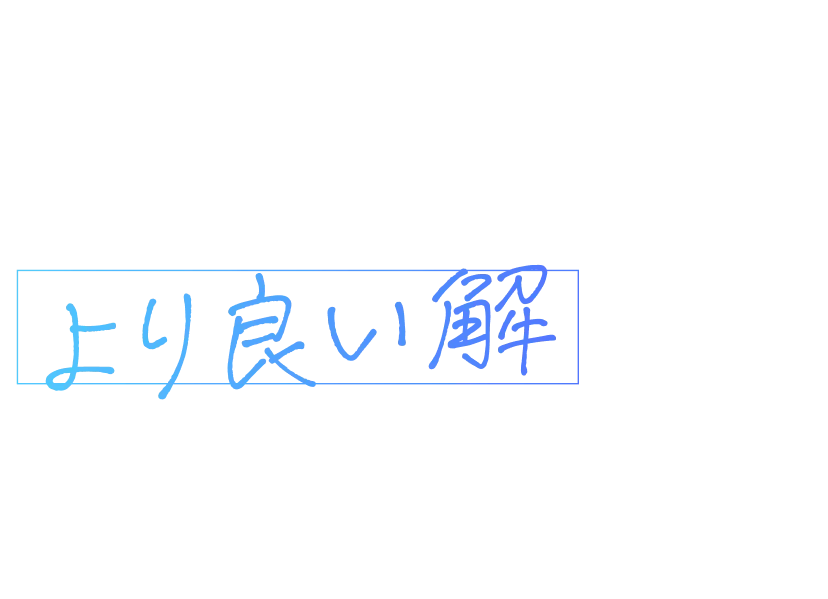








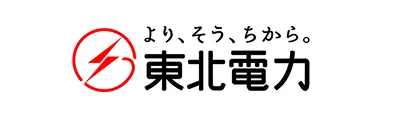
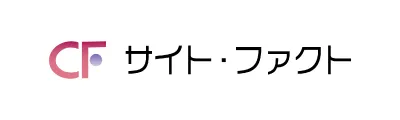


2025.12.19 NEDO「量子コンピュータを用いた社会問題ソリューション開発」に採択
〜量子最適化技術を活用し、多剤耐性菌(MDRO)に対する新たな治療戦略の確立を目指す〜 株式会社EQUESは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が実施する懸賞金活用型プログラム「量子コンピュータを用いた社会問題ソリューション開発(Quantum Computing Challenge)」のスクリーニング審査を通過し、採択されたことをお知らせいたします。 本プロジェクトでは、世界的な脅威となっている多剤耐性菌(MDRO)感染症に対し、量子最適化技術を用いた革新的なアプローチで治療薬開発の加速と新たな治療戦略の構築に取り組みます。 ■ 背景:多剤耐性菌(MDRO)という世界的脅威 抗生物質の広範な使用に伴い、既存の薬が効かない「多剤耐性菌(MDRO)」が世界中で急増しています。感染症による死亡者数は増加の一途を辿っており、従来の抗生物質開発に代わる、あるいはそれを補完する新たな治療戦略の確立が急務となっています。 ■ 本プロジェクトの概要 EQUESは、細菌叢(マイクロバイオーム)を緻密にコントロールすることで病原体の増殖を抑制する手法に着目しています。 具体的には、病原体が生存に必要とする栄養素の供給を遮断するため、複数の「栄養競合細菌」を組み合わせるアプローチを提案します。膨大な細菌の組み合わせの中から、特定の病原体に対して最適なセットを選定する「組合せ最適化問題」に対し、以下の量子技術を適用します。 量子最適化による細菌選定の効率化 多数の細菌候補から、病原体の栄養供給を最も効果的に断つ組み合わせを探索します。従来手法では膨大な計算時間を要するこの課題に量子アニーリング等の手法を適用し、効率的に最適解を導き出します。 量子コンピュータを用いたシミュレーション 常在細菌同士の複雑な相互作用や、病原体への影響を量子計算によってモデル化します。これにより、生体内での治療効果を高い精度で予測し、一人ひとりに最適な治療戦略の立案を支援します。 ■ 期待される成果と今後の展望 本プロジェクトの成功により、MDRO感染症に対する新薬開発のスピードアップと製造コストの削減が期待されます。病院内での二次感染リスクを低減し、患者様の安全を守るだけでなく、将来的には農業分野における「作物と細菌の最適化」など、細菌叢コントロール技術の多分野展開も目指してまいります。 EQUESは、東大松尾研発のスタートアップとして、最先端の数理・AI技術と量子計算を融合させ、医療・製薬業界の課題解決、ひいては社会全体のウェルビーイング向上に貢献してまいります。 NEDO懸賞金活用型プログラムHPはこちら お問い合わせはこちら
2025.12.15 <イベント出展のお知らせ>Start up JAPAN 2025 in 大阪
株式会社EQUESは、2025年12月17日(水)から18日(木)までマイドームおおさかで開催される、スタートアップ業界最大級の展示会「Start up JAPAN 2025 in 大阪」に出展することをお知らせいたします。 Start up JAPAN は、日本、そして世界から約450社の最先端スタートアップが集結する、国内最大級の展示会です。 企業のDX推進や新規事業開発、協業・事業連携のきっかけとなる出会いの場として、多くの業界関係者やビジネスリーダーが来場します。 弊社ブースでは、東京大学・松尾研究室発のAIスタートアップとしての知見を活かした、最先端のAIソリューションや「伴走型技術開発」の取り組みについてご紹介する予定です。 企業のDXを加速させるAIの活用事例や、具体的な業務効率化のアプローチについて、デモンストレーションを交えてご案内いたします。 ご興味をお持ちの方は、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。 イベント詳細はこちら ⬛︎ 開催概要 名称: Start up JAPAN 2025 in 大阪 開催日時: 2025年12月17日(水)~18日(木) 10:00~17:00 会場: マイドームおおさか(大阪商工会議所) 主催: Eight(Sansan株式会社)
2025.12.02 【四国初】「量子コンピュータ×AIセミナー in 愛媛」にEQUESメンバーが登壇いたします
この度、2025年12月10日(水)に愛媛大学にて開催される、日本量子コンピューティング協会主催のイベント「量子コンピュータ×AIセミナー in 愛媛」に、株式会社EQUES Lead Engineering Managerの武藤 雅裕が登壇いたします。 本イベントは、四国初となる量子技術とAIに関する最先端の情報が集結するセミナーです。 第一部(13:10-15:30)では、量子コンピューターとAIの最新の動向や事例について、国内外の取り組みや動きを紹介します。弊社EQUESの武藤は、「生成AIと量子コンピューティングの応用」をテーマにお話しさせていただきます。 現地参加のほか、オンラインでの参加も可能ですので、ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。 参加申し込みはこちらから 登壇者プロフィール 武藤 雅裕(Masahiro Muto) 株式会社EQUES Lead Engineering Manager 長年クラウドエンジニアとしてインフラ基盤の開発に従事した後、2024年に専門をクラウドコンピューティングからコンピュータービジョン・生成AIへ移行。2025年6月に東大松尾研発のスタートアップである株式会社EQUESに入社。現在は生成AI全般のリードエンジニアリングマネージャーとして活躍する傍ら、量子コンピュータと生成AIの融合領域を探求。日本量子コンピューティング協会の量子ジェネラリスト資格も保有。 イベント開催概要 イベント名:量子コンピュータ × AI セミナー in 愛媛 開催日時:2025年12月10日(水) 13:00 - 17:00 会場:愛媛大学 共通講義棟C EL43講義室(オンライン参加も可能) 参加費:無料 主催:日本量子コンピューティング協会 申込締め切り:2025年12月5日(金) 皆様のご参加を心よりお待ちしております。 参加申し込みはこちらから
Service

EQUESは、高い専門性による創出力を、現場への価値変換力とスピードによって、
シームレスに産業へとつなげることを強みとしています。
EQUESは多くの企業とパートナーシップを結んでいます。 ※一部抜粋
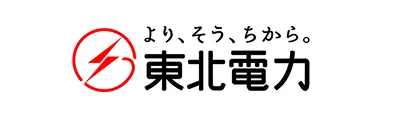








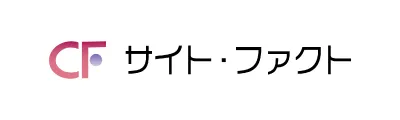


Example

AI×DX寺子屋|茨城県立竜ヶ崎第一高校・附属中学校で「未来の教室」を開催
2025.11.17
中高生が「AIエージェント」で地元企業の課題解決に挑む 株式会社EQUESは、2025年10月18日に茨城県立竜ヶ崎第一高等学校・附属中学校(以下、竜ヶ崎第一高校・附属中学校)で開催された「ホンモノのキャリア教育プログラム」において、「未来を拓くAI×人のチカラ」をテーマにした特別授業を実施しました。本授業は、生徒がAIの現代ビジネスにおける重要性や最先端技術「AIエージェント」について理解を深め、地元企業のリアルな課題解決に挑む、新しい形のAI×ビジネスワークショップとして展開されました。 開催の背景:学校の想いとEQUESの「AI×DX寺子屋」 今回の特別授業は、同校の太田垣校長先生から頂いた「次世代を生きる生徒たちに“ホンモノ”のキャリア教育を提供したい」というご相談がきっかけとなりました。 このご要望に対し、弊社が推進するAI相談サービス「AI×DX寺子屋」のカスタマイズプランを活用。「ビジネスにおけるAIエージェントの台頭」という未来を見据え、AIと“協働”するとはどういうことかを考える、未来創造型のAI×ビジネス授業として実施する運びとなりました。 また、地元企業の実際の課題を題材にすることで、生徒の柔軟な発想が企業に新たな視点をもたらすとともに、生徒自身の地元企業への理解と愛着をも深める、地域全体でのWin-Winな関係構築を目指しました。 【ご協力いただいた地元企業・研究機関様のご紹介(一部:掲載許可を頂いた企業様のみ)】 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 様 株式会社 常陽銀行 様 株式会社タナカ 様 高エネルギー加速器研究機構 様 一誠商事株式会社 様 授業概要:AIエージェントで未来のビジネスをデザインする 当日の授業は、講義とワークショップの二部構成で実施しました。 1. 講義:AIとビジネスの関係 授業前半では、当社スタッフが登壇。EQUESが手掛ける「伴走型技術開発」や「製薬AI事業」などの具体的なAIソリューション事例を紹介するとともに、「なぜ今、ビジネス環境にAIが必要なのか」、そして「AIエージェント」という最先端技術が未来をどう変えるかについて解説しました。AIが単なるツールではなく、ビジネスのあり方そのものを変革する力を持っていることを伝えました。 2. ワークショップ:AIエージェントを活用して地元企業の課題を解決する 後半は、3〜4人のグループに分かれ、「地元企業の課題を分解し、それを解決するAIエージェントを考える」というテーマで実践的なワークショップを実施。生徒たちはAIやPCツールを積極的に活用しながら活発に意見を交換しました。最終的には溢れたアイデアをワークシートにまとめ、教室に設置されたモニターを使って発表を行いました。 (↑写真:常陽銀行様のワークシートの例。生徒は、若者と高齢者など、世代や環境によってサービスを利用したくなる条件は大きく異なっているため、それぞれに合った施策が必要だと考え提案を行いました。) 授業の雰囲気:技術的な質問が飛び交う、ハイレベルな議論 初対面のグループが多い中、すぐに打ち解けて目標に向けた建設的な話し合いが始まり、和気藹々とした雰囲気ながらも白熱した議論が展開されていました。 生徒の皆さんからは沢山の新しい発想が提案され、「アイデアはたくさん出るが、どう企業のサービスと合致させていけばいいのか」などといった発展的な悩みの声が聞かれるなど、その想像力の豊かさには驚かされました。 また、講師陣に寄せられた質問は、「その技術は具体的にどうやって実現するのか?」「ビジネスとしての実現可能性は?」といった、技術的な側面や事業性にまで踏み込むハイレベルなものばかりでした。 (↑写真:講義中の雰囲気。生徒様は熱心に授業に耳を傾け、新しいAIエージェント技術の概要に興味津々でした。) 校長:太田垣先生のコメント 飛ぶ鳥を落とす勢いのAIビジネスから中高生のために貴重なお時間をいただき、心より感謝申し上げます。「AIエージェント」というリクエストに応え、単なる座学ではなく動きながら身に付けるワークショップ型の講座にまとめ上げていただいた情熱と使命感に敬意を表します。準備や進行についても教職員と緻密な調整を重ねていただき、参加した生徒・保護者にも大満足の質の高い講座を一緒に作り上げることができました。 私たち竜一は今後も時代の先頭を走る生徒たちを育てていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 EQUESより:未来のイノベーターたちへの期待 今回、竜ヶ崎第一高校・附属中学校という非常に意欲的な生徒の皆さんとお会いでき、私たち自身も大きな刺激を受けました。 「AIエージェント」は、まだ社会に普及し始めたばかりの新しい技術です。それを中高生のうちからビジネスの視点で考え、具体的な実現可能性まで踏み込んで質問する生徒たちのポテンシャルに、深く感銘を受けています。 今回の授業が、生徒の皆さんが未来のイノベーターとして羽ばたくための一助となれば幸いです。EQUESは今後も、最先端のAI技術を社会に結ぶ架け橋となる活動を続けてまいります。 今回の授業を実現した「AI×DX寺子屋」について 「AI×DX寺子屋」は、東大生・東大出身者が7割を占めるEQUESのメンバーが、AIやDXに関する素朴な疑問や困りごとをチャットで回答し、お客様のAI活用やDX推進をサポートするサービスです。 AI専門家集団への相談し放題、AIツールの活用提案を特徴とする月額制の「プランA」のほか、今回のようなAI人材研修の実施、技術顧問、開発支援など、お客様の要望に応じて柔軟に内容を決定する「プランB(応相談)」も提供しています。 皆様がAIと歩む未来を創造する一助となれば幸いです。 AI×DX寺子屋の詳細はこちら

SOLIZE PARTNERSが語る、製造業のDXにおけるAI活用のはじめの一歩
2025.10.31
■導入企業の紹介 SOLIZE PARTNERS株式会社(以下SOLIZE PARTNERS)は、日本で初めて3Dプリンターを導入して以来、長年にわたり日本のものづくりを支えているデジタルエンジニアリングのパイオニアです。昨今は社内のデジタルトランスフォーメーション(DX)にも取り組まれており、熟練技術のデジタル化による普及やAIを活用した新しいソリューション開発に注力されています。このたび、株式会社EQUESは、SOLIZE PARTNERSのAI技術導入による課題解決を支援するため、AI PoC(概念実証)サービス『ココロミ』を提供いたしました。導入から運用までの様子をインタビューさせていただきましたので、AI技術導入をお考えの方はぜひご一読ください。 ■SOLIZE PARTNERSの課題 SOLIZE PARTNERSがAI技術の導入において抱えていた課題は、「熟練技術者の頭の中にある情報をどうやってシステム化するか」というものでした。 AIによるDXを進めるにあたって、これまで熟練者が経験によって培ってきた感覚的で言葉にならないノウハウを、いかにAIのシステムに組み込み、活用に漕ぎつけるかという課題は、SOLIZE PARTNERSに限らずものづくり業界全体のDXにおける大きなボトルネックとなっています。 AI導入のプロジェクトを始めるにあたって、この課題を解決するべく、PoC(概念実証)からその分析、アクションプランの策定までを包括的に行う弊社サービス「ココロミ」が導入されました。 ■導入の経緯 「熟練技術者の頭の中にある情報をどうやってシステム化するか」という課題の中で、AIを活用する目的として立ち上がったのが「複数視点からの画像入力を用いた部品特徴の網羅的な検出」というテーマでした。 このテーマを軸に、SOLIZE PARTNERSとEQUESの共同検討がスタートしました。 ココロミを導入する決め手は、弊社が3D生成に関する豊富な経験を有していたことでした。例えば、株式会社セガ様との事業においては、ユーザが簡単なキーワード入力を行うだけでボクセル形式の3Dモンスターを生成するAIを開発した実績があります。(詳しくはこちら)。この開発をSOLIZE PARTNERSに認知していただいたことがご縁となり、共同開発が実現しました。 ■導入後の成果 ココロミでは、以下の2つのテーマでPoC(概念実証)を実施し、それぞれに新たな成果を得ることができました。 取り組み1:設計ナレッジの提案支援 最初の取り組みでは、特定の形状データから特徴を抽出し、それをもとに設計ナレッジを自動で提案するAIの実現性を検証しました。その結果、開発現場で直接活用できるレベルの設計知識をAIが提示できることを確認。従来のように過去資料や文献を検索する手間をかけずに、設計のヒントを得られるようになり、知見の再利用性が大きく高まりました。 取り組み2:3D CADデータの自動生成 次の取り組みでは、自然言語による指示からAIが適切な3D CADデータを生成できるかどうかを検証しました。その結果、単純な形状や構成であればAIによる自動生成が可能であることを確認しました。一方で、複雑な形状を扱う際には、構成部品となる要素データを事前に十分整備しておく必要があることも明らかになり、今後の改善の方向性が見えてきました。これらの検証を通じて得られた成果は、SOLIZE PARTNERSにおけるAI活用を現場レベルへ展開するための第一歩となりました。 ■ココロミ導入を通しての感想 ココロミの推進において、EQUESの徹底した伴走が大きな安心感につながったとのお言葉をいただきました。開発中、多くの技術的懸念や疑問に対し、担当PMエンジニアが都度、論理的な裏付けをもって丁寧に説明させていただきました。技術的な不確実性のあるテーマであったからこそ、一貫した伴走と安心感が、『ココロミ』の提供価値を高め、開発を成功に導くための心の支えとなったと評価いただいています。 さらに、AIという新しい技術への挑戦は、社内への新しい風となり、社員の意識を新たにする理由に繋がりました。 単なる技術検証に留まらず、AI活用に対する社内全体の意識を変革するという、文化的な成果も生まれました。 ■今後の展望 今回の『ココロミ』を通じて得られた知見と信頼関係を基に、SOLIZE PARTNERSはAI技術の応用をさらに深化させていく意向を示されています。 SOLIZE PARTNERS側の担当者様は、「ぜひ次の取り組みをやりたい」と力強く語り、自社の取り組みを継続していく決意を表明されました。 そして、今後の重要なテーマの一つとして、XAIの必要性が挙げられました。 (XAIとは…「説明可能なAI(Explainable AI)」の略。AI、特にディープラーニングは、なぜその結論に至ったのかという判断プロセスが複雑で、人間には理解しにくい「ブラックボックス」状態になることがある。XAIは、このブラックボックスの中身に説明を与え、AIの判断根拠や理由を人間が理解できる形で示すための技術やその研究分野を指す。AIの信頼性と透明性を高め、医療や金融、自動運転など、高い安全性が求められる分野で公正に活用されることを目指している。) SOLIZE PARTNERS側の担当者様は、「ブラックボックスになってしまいがちなAIの判断に説明の有無があることで、現場での意思決定に使えるかどうかは大きく変わる」と、実務における説明責任の重要性を強調されました。 株式会社EQUESは、『ココロミ』を通じて培われた具体的な知見と技術的な基盤をもとに、SOLIZE PARTNERSの新たな価値創造と産業の高度化を引き続き力強く支援してまいります。 SOLIZE PARTNERS HPにて、弊社CEO岸および本プロジェクトPMの村山のインタビューが掲載されております。詳しくはこちらからご覧ください。
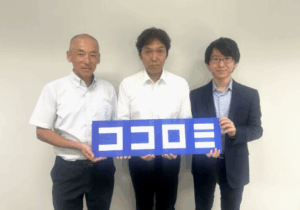
AI-OCRで製造現場の記録を自動化|Cyto-Factoの導入事例
2025.10.23
―導入した会社の紹介 Cyto-Facto(サイトファクト)は、神戸に拠点を置く細胞・遺伝子治療分野に特化したCDMO企業です。FBRIの細胞治療研究開発センターを継承し、PIC/S GMP準拠の製造体制を整備。開発から製造、品質試験まで一貫支援し、独自のシステムによるDX推進で、安全かつ高品質な先端治療の社会実装を目指しています。 ― 今回のプロジェクトを始められた背景について教えてください。 製造現場では、通信機能のない機器が多く残っており、液晶パネルや制御PCの画面に表示される情報を作業員が手作業で記録していました。従来のOCR技術では操作が難しい上、読み取り精度も不安定で、業務効率化には限界があったのです。そこで私たちは、AI-OCR技術を活用し、画像認識とデータ抽出の精度向上を目指すプロジェクトを立ち上げました。 ― 具体的にはどのような取り組みをされたのでしょうか? まず、液晶パネルや制御PC画面から取得した画像データをAI-OCRで読み取り、MESやLIMSへ自動入力する仕組みを検討しました。さらに、UIモック版やクラウド版のOCRシステムを開発し、音声入力によるデータ修正機能(日本語・英語対応)も実装しています。また、GMP/GCTP規制を考慮したインターフェース設計にも取り組みました。 ― 開発パートナーにEQUESを選ばれた理由は何ですか? EQUES様は高精度AI-OCR技術の開発実績を持ち、医療や製造分野でのGMP対応経験が豊富でした。また、オフライン環境でのOCR対応力やMES/LIMSとの連携を見据えた提案力・技術力も魅力的でした。複数の課題に対し具体的な解決策を提示していただいたことも大きな決め手です。 ― これまでにどのような成果が得られていますか? UIモック版OCRの社内動作を確認済みで、音声入力によるデータ修正機能のデモも実施しました(日本語・英語対応)。さらに、GPTモデルを活用したクラウド版OCRの開発も進行中です。サンプル画像では100%の認識精度を達成しており、GMP対応を見据えた修正履歴管理機能の設計にも着手しています。 ― 現場からの反応はいかがでしょうか? 「計画通りに開発が進んでいる」「進捗共有がタイムリーで非常にスムーズ」「本開発に向けた準備が円滑に進んだ」といった声が多く寄せられています。現場にとっても大きな期待感につながっていると感じています。 ― 今後の展望を教えてください。 今後は、GMP/GCTP対応を含めたインターフェース設計の詳細化を進めていきます。さらに、iOSやAndroidに対応したアプリの開発や、動画・動的テロップの認識といった新たな機能拡張にも取り組んでいく予定です。
Member

東京大学大学院.ex 松尾研プロジェクトマネジャー.
松尾研起業クエスト1期生.
松尾研チーフAIエンジニアとして企業との共同研究に従事.その後,現実世界と情報学の融合を志し,計数工学科在学時にEQUESを創業.専門はシステム情報学,特にテラヘルツ波通信とハプティクス(触覚技術).

東京大学大学院. ex 松尾研プロジェクトマネジャー
松尾研起業クエスト2期生.産総研「覚醒」事業採択.
AIビジネスコンテスト全国優勝後,計数工学科で現CEO岸と出会いEQUESを創業.
専門は数理情報学であり,クラスタリング最適化や医療AI分野の研究でトップジャーナルや国際会議に採択されている.

Advisor
松尾 豊
技術顧問
2007年より,東京大学大学院工学系研究科准教授. 2019年より教授. 専門分野は,人工知能,深層学習,ウェブマイニング. 人工知能学会からは論文賞(2002年),創立20周年記念事業賞(2006年),現場イノベーション賞(2011年),功労賞(2013年)の各賞を受賞. 2020-2022年,人工知能学会,情報処理学会理事. 2017年より日本ディープラーニング協会理事長. 2019年よりソフトバンクグループ社外取締役. 2021年より新しい資本主義実現会議 有識者構成員. 2023年よりAI戦略会議座長.
Column

GMP文書とは?AIで作成・管理を効率化する製薬品質保証の新しい方法
2025.12.12
製薬業界における品質保証の現場で、「GMP文書」の作成や管理に多くの時間を費やされている方も少なくないのではないでしょうか。度重なる改訂作業、レビューの往復、そして査察への備えなど、その業務は膨大で、ヒューマンエラーのリスクも常につきまといます。求められる品質基準は年々高まる一方で、リソースは限られている、そんなジレンマを抱えているかもしれません。 この記事では、医薬品の品質を守るために不可欠なGMP文書の基礎知識から多くの品質保証(QA)部門が直面している具体的な課題、そしてそれらの課題をAIの力でどのように解決できるのかまでを分かりやすく整理します。 この記事を読み終える頃には、GMP文書管理の現状を打開するヒントが見つかり、業務効率化に向けた新たな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。 弊社(株式会社EQUES)は、製薬分野に強く、経済産業省のGENIACにも採択されたGMP文書業務効率化SaaS「QAI Generator」サービスを展開しております。事例集もございますのでぜひご活用ください。 製薬DX事例集はこちらから 製薬DXに関する無料相談はこちらから GMP文書とは?その重要性と基本を解説 GMP文書について理解を深めるために、まずはその土台となる「GMP」そのものについて確認しておきましょう。 GMPとは?医薬品の品質を守るルール GMPとは「Good Manufacturing Practice」の略語で、日本語では「製造管理及び品質管理の基準」と表現されます。中でも医薬品に関わるGMPのことを医薬品GMPと呼びます。 医薬品は、人の健康や生命に直接影響を与えるものです。そのため、万が一にも品質に問題があってはなりません。医薬品GMPの目的は、製造過程での人為的な誤りを最小限にすること、医薬品の汚染や品質低下を防ぐこと、そして常に高い品質を保証するシステムを設計することにあります。 このGMPの基準は、厚生労働省令(「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」)が定めており、一般に「GMP省令」と呼ばれています。 GMP文書の役割と法的な位置づけ GMP省令では、このGMPを確実に実行するために、いわゆる「GMPの三原則」が基本理念として示されています。 人為的ミスの防止 医薬品の汚染および品質低下の防止 高い品質を保つ仕組みづくり これらの原則を実現するために不可欠なのが「文書化」です。GMP省令では、製造所の職員の責務や管理体制を文書によって適切に定めること や、作業手順を文書化してマニュアル通りに作業させ、それを記録することが求められています。 つまりGMP文書とは、GMP省令という法律に基づき、医薬品の品質を保証する仕組みを構築し、その仕組み通りに業務が実行されたことを証明するために作成・管理される、すべての文書と記録のことを指します。 医薬品GMP文書にはどんな種類がある?主な文書と管理プロセス 医薬品GMP文書と一口に言っても、その種類は多岐にわたります。これらは大きく4つのカテゴリーに分類することができます。 主な医薬品GMP文書の種類(基準書、手順書、記録書など) GMP省令で要求される文書は、主に以下の4つに分けられます。 製品標準書 医薬品の品目ごとに、製造承認された内容や製造手順、品質規格、試験方法などをまとめた、その製品の「憲法」とも言える文書です。 基準書 製造所全体で守るべき基本的なルールを定めた文書です。 (例)衛生管理基準書、製造管理基準書、品質管理基準書 手順書 (SOP: Standard Operating Procedures) 基準書に基づき、個々の作業や業務を「誰が、いつ、どのように行うか」を具体的に定めた文書です。 (例)変更の管理に関する手順書、逸脱の管理に関する手順書、自己点検に関する手順書、教育訓練に関する手順書、文書及び記録の管理に関する手順書など、非常に多くの種類があります。 記録書 手順書に基づいて作業や試験を実施した結果を記録する文書です。作業が正しく行われたことを証明する「証拠」となります。 (例)製造指図書に基づく製造記録、試験検査記録、変更申請書(変更記録)、自己点検記録、教育訓練記録 医薬品GMP文書の作成・承認・保管・改訂のライフサイクル これらの医薬品GMP文書は、一度作成したら終わりではありません。常に最新かつ最適な状態を保つために、一連のライフサイクル(作成→承認→配布・教育→実行→保管→改訂→廃棄)に沿って適切に管理される必要があります。 特に保管については、例えば記録書は作成日から5年間(ただし有効期間+ 1年が5年より長い場合はその期間)の保管の義務(GMP省令第20条より)など、厳格なルールが定められています。 多くの企業が抱えるGMP文書管理の課題 GMP文書は医薬品の品質保証の根幹ですが、その管理には多くの課題が伴います。特に従来の紙ベースや手作業での運用では、以下のような問題が発生しがちです。 作成・レビューにかかる膨大な時間と人的コスト GMP文書の作成、特にSOP(手順書)の新規作成や改訂には、多くの時間と労力が必要です。さらに、作成された文書は複数の部門や担当者によるレビューと承認を経る必要があり、このプロセスが長期化することも少なくありません。手書きやExcelでの文書作成は、時間がかかるだけでなく、貴重な専門人材のリソースを圧迫する大きな要因となっています。 整合性の担保とヒューマンエラーのリスク GMP文書は、製品標準書を頂点として、基準書、手順書、記録書が互いに関連し合っています。紙ベースの管理では、一つの文書を改訂した際に、関連する他の文書への反映が漏れてしまう「不整合」のリスクがあります。 また、「用語の表記ゆれ」、旧版の文書を誤って参照してしまう、あるいは手書きによる記載ミスや読み間違い といったヒューマンエラーも起こりやすくなります。 査察対応とデータインテグリティの課題 当局による査察(ささつ)の際には、要求された文書や記録を迅速に提示する必要があります。しかし、紙の文書が書庫に膨大に保管されている場合、必要な文書をすぐに探し出すのは困難です。また、文書の紛失や劣化のリスク も伴います。 近年重視されている「データインテグリティ(データの完全性・正確性・信頼性)」の観点からも、手書きの記録は「いつ誰が変更したか」の追跡が難しく、データの信頼性を担保しにくいという課題があります。 薬機法の改正による規制の厳格化 2025年に施行された改正薬機法では、MAH(製造販売業者)による製造所の管理監督責任がより一層強化され、製造業者自身のGMP省令遵守も薬機法上で直接義務化されるなど、規制は厳格化しています。 PMDA(医薬品医療機器総合機構)においても、2025年4月から「医薬品品質管理部」に検定・検査課が新設されるなど、適合性調査(査察)の体制が強化されています。こうした背景から、査察や監査に対する文書管理の重要性は、ますます高まっていると言えるでしょう。 (参考元: 2024年度 GMP / GCTP Annual Report) AIで変えるGMP文書業務の未来 - QAI Generatorのご紹介 こうしたGMP文書に関する根深い課題を解決する鍵として、今、AI(人工知能)の活用が注目されています。 AI活用がGMP文書業務にもたらす変革 AI、特に文章生成を得意とするAI技術は、GMP文書の作成・管理プロセスを劇的に変える可能性を秘めています。 例えば、膨大な時間がかかっていた文書の新規作成や改訂案の作成をAIがサポートすることで、担当者はより専門的な判断やレビュー業務に集中できます。また、AIによるチェック機能は、表記ゆれや参照漏れといったヒューマンエラーの防止にも貢献します。 EQUESの「QAI Generator」とは? 弊社、株式会社EQUESは、東京大学松尾研究所発のベンチャーとして、AIを用いた「伴走型技術開発」で企業様をサポートしております。特に強みを持つ製薬分野において、GMP文書業務の課題を解決するために開発したのが、製薬品質保証のGMP文書業務効率化SaaS「QAI Generator」です。 「QAI Generator」は、難解な操作を必要としません。簡単な質問に答えていくだけで、必要な書類や法務書類をAIが自動で作成します。 「QAI Generator」が実現する具体的な業務効率化 「QAI Generator」の導入により、GMP文書業務の効率は飛躍的に向上します。実際に導入いただいた企業様では、文章の作成時間が5割カットされ、さらにレビュー時間も7割以上短縮されたという実績が報告されています。 これは、AIがたたき台を作成することで「ゼロから書く」負担をなくし、同時に表記ゆれや形式の不備を減らすことで、レビューの手戻りを大幅に削減できるためです。 「QAI Generator」は、経済産業省のGENIACにも採択されており、その技術と将来性が高く評価されています。 GMP文書ツール導入で失敗しないためのポイント AI活用を含め、GMP文書の管理ツールを導入する際には、いくつかの重要なポイントがあります。 自社の課題とツールの機能がマッチしているか まずは、自社が抱える最大の課題がどこにあるのかを明確にすることが重要です。「文書の作成時間を短縮したいのか」「文書の検索性を高めて査察対応をスムーズにしたいのか」「文書の版管理や承認プロセスを電子化したいのか」によって、選ぶべきツールは異なります。 「QAI Generator」は、特に「文書作成とレビューの時間を大幅に削減したい」という需要に強いツールですが、ご要望に合わせて様式をカスタマイズすることを前提としており、幅広いニーズに対応することができます。 製薬AI DX無料相談はこちら サポート体制と専門知識の有無 GMP文書は専門性が高く、業界特有の要件が多数存在します。そのため、ツールを提供するベンダーが製薬業界やGMPの業務プロセスを深く理解しているかどうかが、導入成功の鍵を握ります。万が一トラブルが起きた際や、運用方法に悩んだ際に、専門知識を持った担当者による手厚いサポートを受けられるかを確認しましょう。 弊社EQUESは製薬分野に特に強みを持っており、またAI専門家集団がお客様の困りごとに寄り添うサービス(AIDX寺子屋)も展開しておりますので、導入後も安心してご相談いただけます。 まとめ 今回は、医薬品の品質保証の要である「GMP文書」について、その基本から管理上の課題、そしてAIによる解決策までをご紹介しました。 GMP文書とは、GMP省令に基づき、医薬品の品質を保証する仕組みと実行を証明する文書群です。「製品標準書」「基準書」「手順書」「記録書」など多様な種類があります。GMP文書の管理は、法律で定められた義務であると同時に、多くの企業にとって大きな負担となっている現実があります。従来の紙や手作業による管理では、作成・レビューの時間、ヒューマンエラー、査察対応の非効率性といった課題がありました。AIを活用した「QAI Generator」のようなツールは、これらの課題解決に有効です。簡単な質問に答えるだけでAIが文書を自動作成します。実際の導入例では、作成時間が5割、レビュー時間が7割以上も短縮されています。 もし、貴社がGMP文書の作成・管理に課題を感じていらっしゃるなら、AIの力を活用してみませんか。 弊社(株式会社EQUES)は、製薬分野に強いAI専門家集団 として、貴社の業務効率化を全力でサポートします。ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。 製薬AI DX無料相談はこちら

データインテグリティとは?製薬GMPでの重要性とAI活用の未来
2025.12.12
医薬品の品質保証や品質管理の現場において、膨大な文書作成やデータの整合性確認に追われ、頭を悩ませてはいませんか? 近年、製薬業界では「データインテグリティ(データの完全性)」への対応が厳格化されており、現場の負担は増すばかりです。しかし、要件を正しく理解し、適切なツールを活用することで、リスクを減らしながら業務を効率化することが可能です。 この記事では、データインテグリティの基本からALCOA原則、そして最新のAI技術を用いた解決策までをわかりやすく解説します。 この記事を読み終える頃には、データインテグリティ対応への不安が解消され、実務の効率化に向けた具体的な一歩が見えてくるはずです。 製薬DX導入事例の資料請求はこちら データインテグリティとは?製薬業界で求められる背景 まず、「データインテグリティ(Data Integrity)」という言葉の意味と、なぜ今、製薬業界でこれほどまでに重要視されているのかを解説します。 データインテグリティの定義 データインテグリティとは、直訳すると「データの完全性」や「データの整合性」を意味します。製薬業界においては、データのライフサイクル全体を通じて、データが「完全で、一貫性があり、正確であること」を指します。 具体的には、医薬品の製造や品質管理の過程で生成されたデータが、改ざんや欠落なく、事実そのものであることを保証する概念です。 注目される背景と規制の強化 近年、国内外でデータ改ざんや不適切なデータ管理による品質問題が相次いで報告されました。これを受け、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)やPIC/S(医薬品査察協定・医薬品査察共同スキーム)といった規制当局は、データ管理に対する監視を強めています。 特にPMDAは「医薬品の製造管理及び品質管理の基準(GMP)ガイドライン」等の各種ガイドラインの中で、データの信頼性確保を強く求めています。適切なデータインテグリティ対応ができていない場合、規制当局からの指摘事項となり、最悪の場合、業務停止命令や社会的信用の失墜につながるリスクがあります。 GMPにおけるデータインテグリティと「ALCOA原則」 GMP(Good Manufacturing Practice:医薬品の製造管理及び品質管理の基準)の現場でデータインテグリティを確保するために、必ず押さえておくべき基準が「ALCOA(アルコア)原則」です。 ALCOA(アルコア)原則とは ALCOA原則とは、データの信頼性を担保するために満たすべき5つの要件の頭文字をとったものです。 A:Attributable(帰属性)誰が、いつその作業を行ったかが明確であること。作業者の署名やタイムスタンプなどが該当します。 L:Legible(判読性)データが読みやすく、長期にわたって保存・参照可能であること。手書きの記録が汚れて読めないといった状態はNGです。 C:Contemporaneous(同時性)作業が行われたその時に記録されていること。後から記憶を頼りに記録する「バックデート」は認められません。 O:Original(原本性)最初に記録されたデータ、または認定された写しであること。 A:Accurate(正確性)データが事実通りであり、誤差や修正がある場合はその履歴が残っていること。 これらの原則は、紙の記録だけでなく、電子データにおいても同様に適用されます。 さらに進化した「ALCOA+(アルコアプラス)」 近年では、上記の5つに加えて、以下の4つの要素を加えた「ALCOA+(CCEA)」の遵守も求められています。 Complete(完全性): データが欠落なくすべて揃っていること。 Consistent(一貫性): データの日時や順序に矛盾がないこと。 Enduring(耐久性): データが記録媒体に長期間保存され、消失しないこと。 Available(利用可能性): 必要なときにいつでもデータにアクセスできること。 これらを徹底することは、製品の品質を保証し、患者様の安全を守るための「義務」であるといえます。 データインテグリティへの対応のポイントと実務 では、具体的にどのように対応を進めればよいのでしょうか。 GMPの現場においてデータインテグリティを確保するためには、単にシステムを導入するだけでなく、「ガバナンス」「技術」「手順」の3つの側面から包括的に対策を講じる必要があります。 ① ガバナンス:経営層のコミットメントと企業風土 データインテグリティ対応の第一歩は、現場の担当者ではなく、経営層(シニアマネジメント)の姿勢にあります。 品質文化(Quality Culture)の醸成: 「悪い報告をしても責められない」「データの隠蔽や改ざんが許されない」というオープンな企業風土を作ることが不可欠です。現場が納期やコストのプレッシャーから不正に手を染めないよう、経営層がリソース(人員・時間)を適切に配分する必要があります。 教育・トレーニングの徹底: 全従業員に対し、データインテグリティの重要性と、不正が患者様の命に関わるリスクであることを定期的に教育します。 ② 技術的対策(Technical Controls):システムによる制御 意図しないミスや不正を防ぐため、コンピュータ化システムには以下の機能要件が求められます。 アクセス管理の厳格化: ユーザーごとに固有のIDとパスワードを発行し、共有(使い回し)を禁止します。また、管理者(Administrator)権限と、分析を行う担当者(User)の権限を明確に分離し、担当者が自分のデータを削除・変更できない設定にします。 監査証跡(Audit Trail)のレビュー: 「誰が、いつ、何を、なぜ変更したか」を自動記録する監査証跡機能を有効にします。重要なのは記録することだけでなく、その履歴を定期的にレビュー(点検)し、不審な操作がないかを確認するプロセスを構築することです。 ③ 手順的対策(Procedural Controls):人の行動とルールの徹底 システムで制御しきれない部分(紙の記録や手作業)は、SOP(標準作業手順書)でカバーします。 ブランクフォーム(空欄用紙)の管理: 「良い結果が出るまで何度も試験を行い、悪い結果の記録を捨てる」といった行為を防ぐため、発行枚数を管理した番号付きの記録用紙(ブランクフォーム)を使用し、書き損じも含めて全て回収・保管します。 生データの定義と保存: 何をもって「原本(オリジナル)」とするかを定義します。電子天秤の印字レシートや、チャート図などの生データは、劣化しないよう適切に保存する必要があります。 ④ リスクマネジメント:データライフサイクルの把握 すべてのデータに同じ労力をかけるのではなく、リスクベースアプローチを採用します。 データライフサイクルの特定: データが生成されてから、処理、保存、アーカイブ、廃棄されるまでの流れ(ライフサイクル)を可視化します。 リスク評価(Risk Assessment): データの重要度や、改ざん・ミスの起きやすさを評価し、リスクが高いプロセスに優先的に対策リソースを投入します。 現場が抱える「文書作成」の負担と課題 これらの対策(SOPの整備、リスク評価書の作成、監査証跡のレビュー記録など)をすべて実行するには、膨大な文書作成業務やチェック業務が発生します。 「手順書と実際の記録に齟齬がないか」「法規制の最新版に対応できているか」といった確認作業は、すべて人の手で行うには限界があります。薬機法が年々厳格化していく中、多くの品質保証担当者が本来注力すべき品質改善業務よりも、書類の整合性チェックに多くの時間を奪われているのが現状です。 AI活用で変わる品質保証 | QAI Generatorのご紹介 こうした課題を解決し、データインテグリティの確保と業務効率化を両立させる手段として、AI(人工知能)の活用が注目されています。 AIによる自動化でヒューマンエラーを削減 最新のAI技術を活用することで、これまで人が行っていた文書の作成やチェック作業を大幅に効率化できます。AIは疲れを知らず、膨大なデータの中から整合性の不備や記載ミスを瞬時に検出することが可能です。これにより、ヒューマンエラーによるデータインテグリティ欠如のリスクを最小限に抑えることができます。 製薬SaaS「QAI Generator」とは 弊社、株式会社EQUES(エクエス)は、東京大学松尾研究所発のベンチャー企業として、製薬分野に特化したAIソリューションを提供しています。その一つが、製薬品質保証のGMP文書業務を効率化するSaaS「QAI Generator」です。 QAI Generatorの特徴 簡単な質問に答えるだけで文書作成: 必要な情報を入力するだけで、AIが必要書類や法務書類を自動でドラフト作成します。 業務時間を大幅に短縮: 実際に導入いただいた事例では、文章の作成時間を5割カット、レビュー時間を7割以上短縮することに成功しています。 専門家集団によるサポート: 東大出身のAI専門家集団が開発しており、製薬業界特有のニーズや規制にも精通しています6。 QAI Generatorを導入することで、データインテグリティ担保のための文書作成にかかる時間を削減し、皆様がより本質的な品質保証業務に専念できる環境づくりをサポートします。 製薬DX導入事例の資料請求はこちら まとめ 本記事では、製薬業界におけるデータインテグリティの重要性について解説しました。 データインテグリティとは: データの「完全性・一貫性・正確性」を保証することであり、規制当局も監視を強めています。 ALCOA原則の遵守: データの信頼性を守るための9つの要件(ALCOA+CCEA)を理解し、実践する必要があります。 業務効率化の鍵はAI: 厳格化する規制に対応しながら負担を減らすには、AIツールの活用が有効です。 データインテグリティへの対応は、企業の信頼と患者様の安全を守るための最優先事項です。しかし、すべてをマンパワーで解決する必要はありません。 弊社が提供する「QAI Generator」は、GMP文書業務の効率化を強力にバックアップいたします。データインテグリティ対応にお悩みの方は、ぜひ一度、資料請求にて詳細をご覧ください。 製薬AIに関する無料相談はこちらから

LLM開発のすべてが分かる!費用相場から成功する企業選びまで徹底解説
2025.12.12
「自社の業務効率化のためにLLM開発を検討したいが、何から手をつければ良いのか分からない」と悩んでいませんか? 「内製(自社開発)と外注(開発パートナー)はどちらが良いのか」 「実際の開発費用はどれくらいかかるのだろう」 このような疑問を抱え、なかなかプロジェクトを進められないDX推進担当者様や経営者様も少なくないのではないでしょうか。 ご安心ください。この記事では、LLM開発の基本的な進め方から、気になる費用の具体的な相場、そしてプロジェクトを成功に導くLLM開発企業の選び方まで、網羅的に分かりやすく解説いたします。弊社が収集した信頼性の高い一次情報に基づき、貴社にとって最適な開発方針を見つけ出すための合理的かつ具体的な根拠を提示いたします。 この記事を読み終える頃には、貴社のLLM開発プロジェクトの方針が明確になり、自信を持って最適な開発パートナーの候補を選定できるようになっていると嬉しいです。 AI DXの製薬業界事例はこちらから LLM開発が注目される理由:そもそもLLM開発とは何か 近年、AI技術の進化は目覚ましく、特にLLM(大規模言語モデル)は、私たちの働き方を根本から変える可能性を秘めています。Chat GPTの登場以降、多くの企業がこの技術を自社の業務に取り入れようと動いており、それに伴い、LLM開発を専門とする企業への注目度が急上昇しているのです。 LLM(大規模言語モデル)の概要と可能性 そもそもLLM(Large Language Models:大規模言語モデル)とは、大量のテキストデータを学習することで、人間のように自然な文章を生成したり、質問に答えたり、要約や翻訳を行ったりできるAIモデルのことです。 概要: 数十億から数兆にもおよぶ膨大なパラメータ(学習によって調整される数値)を持つ巨大なニューラルネットワークで構成されています。 ビジネスにおける可能性: 業務効率化: 社内文書の自動作成、カスタマーサポートの自動応答など、定型業務の負担を大幅に軽減します。 新規事業創出: 顧客のデータを分析し、パーソナライズされたマーケティング文案を自動生成するなど、創造的なタスクにも活用できます。 このように、LLMは単なる「新しい技術」ではなく、企業の生産性向上と競争力強化に直結する戦略的なツールとして認識され始めています。 LLM開発の進め方:内製・外注のメリット・デメリットを徹底比較 いざLLM開発を始めようと考えたとき、多くの方が直面するのが「自社で開発すべきか(内製)」「専門企業に依頼すべきか(外注)」という選択です。どちらにも一長一短がありますので、貴社の状況に合わせた最適な方法を選びましょう。 内製(自社開発)のメリット・デメリット 内製は、自社のリソースを使って開発を進める方法です。 メリットデメリットノウハウが蓄積する:AI技術の内製化により、将来的な改善や新規開発がスムーズになります。初期投資と固定費が大きい:AI専門人材の採用・育成、高性能な計算リソース(GPUなど)の確保に大きな費用がかかります。業務への最適化がしやすい:自社の細かな業務プロセスやデータに完全に合わせてカスタマイズできます。開発の難易度が高い:LLMのファインチューニングやRAG(Retrieval-Augmented Generation)構築には高度な専門知識が必要で、途中で頓挫するリスクもあります。 外注(開発パートナー)のメリット・デメリット 外注は、LLM開発を専門とする企業にプロジェクトを依頼する方法です。 メリットデメリットスピーディな導入が可能:プロの知見と技術力により、内製よりも早く質の高いシステムを導入できます。コストが高くなる可能性がある:プロジェクト全体の費用は内製よりも高額になる傾向があり、特に運用後のランニングコストも考慮が必要です。リソースの節約:社内のITリソースや人材を確保する必要がありません。ブラックボックス化のリスク:開発プロセスや技術内容が不透明になりやすく、運用開始後に自社で改善しにくい場合があります。 失敗しないための「内製・外注」判断基準 「どちらが良い」という明確な答えはありませんが、貴社のLLM開発の目的や戦略、リソースや費用によって判断基準が変わります。 視点内製(自社開発)が適している場合外注(開発パートナー)が適している場合1. 目的の明確さコア技術の内製化や、極めて深い独自データへのカスタマイズが必要な場合。PoCでの効果検証や、市場投入までのスピードを最優先する場合。2. 人材(リソース)専門のAIエンジニア、データサイエンティスト、PMといった人材を確保・育成できる場合。専門人材の確保が難しく、開発後の運用サポートも外部に任せたい場合。3. コストとリスク開発費用と失敗リスクを長期的に許容でき、ノウハウ蓄積にコストをかけられる場合。初期の潜在的リスク(失敗やリソース確保難)を回避し、費用対効果(ROI)を早期に示したい場合。 1. プロジェクトの性質と目的の明確さ 開発の目的が、内製と外注のどちらを選ぶべきかを決定づける最も重要な要素です。 PoC(概念実証)やスピード重視の導入を求める場合: 特定の業務効率化の効果を早期に検証したい場合や、市場投入までのスピードを最優先する場合、専門知識を持つLLM開発企業への外注が有利です。内製で専門人材を育成・確保する時間とコストを省けます。 判断基準: 3ヶ月以内に成果を出したいか、または、費用対効果(ROI)を明確にしたいか。 コア技術の内製化と深いカスタマイズを求める場合: 将来的にAI技術を自社のコアな競争優位性にしたい場合や、自社の極めて機密性の高いデータに特化した深いカスタマイズが必要な場合、内製の検討価値が高まります。ただし、この戦略は多大な時間と費用、そして高度な専門知識を必要とします。 判断基準: AI技術のノウハウを、将来的に他製品開発にも活用したいか。 2. 人材(リソース)と技術力の確保 内製を選択する上で、最も大きな壁となるのが専門人材の確保です。 社内にAI専門人材がいるか、あるいは育成が可能か: LLM開発に必要なAIエンジニア、データサイエンティスト、そしてプロジェクトを管理するPM(プロジェクトマネージャー)がすでに社内に確保できている場合、または、今後1年以内に育成できる見込みがある場合は内製が選択肢になります。 判断基準: 開発に不可欠な専門人材の人件費と時間が、確保できないことによる機会損失リスクよりも低いか。 継続的な運用・改善のリソースが必要か: LLMは導入後も、性能維持のための監視、新しいデータの学習(再学習)、システムエラー対応などのランニングリソースが必要です。これらのリソース確保が難しい場合は、開発後のサポート体制が整ったLLM開発企業への外注を強くおすすめします。 判断基準: 開発だけでなく、運用フェーズにおける固定費(人件費)を自社で負担し続けられるか。 3. コスト意識とリスク許容度 LLM開発費用とリスクの許容度によって、最適な戦略は変わります。 初期コストを抑えたい場合: 外注は一見高額に見えますが、内製で発生する「失敗した際の採用コスト」「高性能な計算リソース(GPUなど)の調達費用」「開発頓挫による機会損失」といった潜在的かつ巨大なリスクコストを回避できます。 判断基準: 開発失敗のリスクを最小限に抑えたいか。 費用対効果(ROI)を迅速に示したい場合: 経営層に対して、投資対効果を具体的に示す必要がある場合、PoCサービスや伴走型開発を提供しているLLM開発企業に外注し、まず小さな成果を出すことが、次の予算獲得につながる最も確実な方法です。 判断基準: 開発費用を、業務効率化による削減効果(ROI)で早期に回収できる見込みがあるか LLM開発費用の相場と費用対効果の考え方 LLM開発を検討する上で、最も気になるのが費用ではないでしょうか。開発の目的や規模によって費用構造は大きく異なりますが、ここではフェーズごとの相場感と、投資対効果を試算する考え方について解説します。 開発フェーズ別に見るLLM開発の費用相場 LLM開発の費用は、「何を開発するか(独自LLMか、既存LLMの活用か)」によって大きく変動します。 フェーズ概要費用相場(概算)PoC(概念実証)LLM開発の実現可能性と効果を検証。データ準備、プロンプトエンジニアリングなど。300万円〜800万円程度RAG/ファインチューニング既存のLLMに自社データや業界知識を学習させ、精度を向上させる工程。500万円〜2,000万円程度API連携・システム構築LLM機能を社内システムやSaaSに組み込むためのインターフェース開発。1,000万円〜3,000万円程度独自LLMのゼロベース構築自社独自のデータセットで、モデルの基盤から構築する場合(非常に稀)。数億円以上(期間1年〜) ※上記は開発企業の規模や技術レベルによって大きく変動するため、あくまで概算の目安としてご参考ください。特にデータ準備やセキュリティ設計の費用は、プロジェクト全体の費用を大きく左右します。 費用対効果(ROI)を試算するための3つのステップ LLM開発は大きな投資となるため、「投資した費用に対してどれだけの効果が見込めるか」という費用対効果(ROI)の試算が不可欠です。 現在のコストを正確に把握する: AI導入によって削減できる「人件費・時間」を具体的に計算します。例えば、1日3時間かかっている文書作成業務が5割削減された場合、年間で削減できる人件費はいくらになるか、を試算します。 期待効果を数値化する: 「顧客満足度10%向上」「エラー率5%削減」といった、LLM開発によってもたらされる具体的な効果を数値目標として設定します。 リスクを考慮する: ハルシネーション(AIが事実ではないことを生成すること)による損害や、データ漏洩リスクなどの「潜在的コスト」も考慮に入れ、開発企業のセキュリティ体制を確認します。 チェックシート保存推奨: 失敗しないLLM開発企業選定のポイント LLM開発を成功させるためには、信頼できるパートナーを選ぶことが最も重要です。ここでは、LLM開発企業を選定する際に確認すべきポイントを7つご紹介します。 実績と専門性: RAGやファインチューニング、特定の業界(例:製薬、金融)における開発実績が豊富かを確認しましょう。単なるプロンプト作成ではなく、モデル評価の知見を持っているかも重要です。 技術力の透明性: 開発に使用するモデルや技術選定の理由を、高校生でも理解できるくらい分かりやすく説明してくれる企業を選びましょう。技術的な内容を曖昧にする企業は注意が必要です。 コストと透明性: 見積もりが明確で、初期費用だけでなく、モデルの利用料やインフラ費用といったランニングコストについても包み隠さず説明があるか確認します。 セキュリティ対策: 自社の機密データを扱うため、データ保護ポリシーや、LLM特有のセキュリティリスク(プロンプトインジェクションなど)への対策を具体的に提示できるかを確認します。 開発後のサポート体制: 導入して終わりではなく、運用後のモデルの再学習、性能維持、トラブル対応などのサポート体制が整っているかを確認しましょう。 コミュニケーション能力: 専門用語を並べるのではなく、貴社の業務課題に真摯に耳を傾け、同じ目線でLLM開発のゴールを設定してくれるパートナーを選びましょう。 伴走型開発の姿勢: 納品したら終わりではなく、貴社が内製化できるようノウハウ共有や教育支援までサポートしてくれる企業は、中長期的に大きなメリットをもたらします。 企業選び7つのポイントチェックシートはこちらから↓(画像を保存しお使いください) LLM開発で確かな実績を持つ企業:株式会社EQUES LLM開発企業を選ぶチェックポイントを解説しましたが、弊社、株式会社EQUESは、まさに先に挙げた「伴走型」のサポートを強みとし、お客様のAI導入を成功に導くパートナーを目指しています。 LLM開発における貴社の課題を解決に導く、弊社の具体的なサービスをご紹介します。 【事例】製薬業界の業務効率化に特化したSaaS LLM開発は、特定の業界で劇的な効果を発揮します。弊社が開発・提供する製薬SaaS『QAI Generator(キューエーアイ・ジェネレーター)』は、特に品質保証(GMP)文書業務の効率化に貢献しています。 簡単な質問に答えるだけで、必要書類や法務書類をAIが自動作成。 文書の作成時間を5割カット、レビュー時間を7割以上短縮という実績があり、高い費用対効果を実証しています。 東京松尾研究所大学発のベンチャーであり、製薬分野に特に強みを持っています。 QAI Generator のお問い合わせはこちら AI技術の困りごとを解決する「AIDX寺子屋」 「自社でLLM開発を進めたいが、技術的な疑問がすぐに解決できない」「AI技術者の専門知識が不足している」といったお悩みはありませんか? 『AIDX寺子屋』は、東大出身のAI専門家集団が、AIDXに関するあらゆる困りごとをチャットで解決するサービスです。 プランA(月額20万円): 相談し放題に加え、月一回のオンラインミーティングも可能。 プランB(応相談): 大学の講義資料作成、セミナー開催、技術者派遣など、貴社のニーズに合わせた柔軟なサポートを提供しています。 大規模開発前のリスクを最小限にする「PoCサービス」 LLM開発は、本格的な開発に入る前に、本当に効果が出るのかを検証するPoC(概念実証)が非常に重要です。 弊社の『ココロミ』は、大規模開発を行う前のPoCに特化したサービスです。いきなり高額な費用を投じるリスクを抑え、まずは小さな規模で確かな効果を検証してから、次のステップに進むことができます。 スタンダードプラン: 月々250万円から、貴社のニーズに合わせたPoCを計画・実行します。 弊社はAIを用いた「伴走型技術開発」で、LLM開発を成功に導くためのあらゆる段階で、きめ細かくサポートいたします。 LLM開発の無料相談はこちらから まとめ 本記事では、LLM開発を検討されているDX推進担当者様や経営者様に向けて、開発の進め方、LLM開発費用の相場、そして成功に導くLLM開発企業の選び方について詳しく解説いたしました。 LLM開発を成功させる鍵は、貴社の課題に最も適した「内製」または「外注」の戦略を選択し、その上で実績と専門性を持った信頼できる開発パートナーを選ぶことです。 進め方: 内製はノウハウ蓄積、外注はスピーディな導入が可能。 費用相場: PoCは300万円〜、本格的な開発は1,000万円以上が目安となります。 企業選び: 実績、技術力の透明性、そして伴走型サポートの有無を重視しましょう。 弊社株式会社EQUESは、LLM開発における技術的な疑問解決から、大規模開発前のPoC、さらには特定の業界に特化した業務効率化まで、貴社のフェーズに合わせたきめ細かなサポートを提供しています。 LLM開発の方針が定まり、次は具体的なパートナーを探したいとお考えでしたら、ぜひ一度、弊社の『AIDX寺子屋』や『ココロミ』をご検討ください。まずは現在の課題をお聞かせいただくことから、貴社のLLM開発成功を全力で支援させていただきます。 LLM開発の無料相談はこちらから